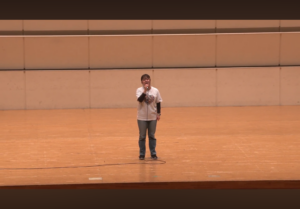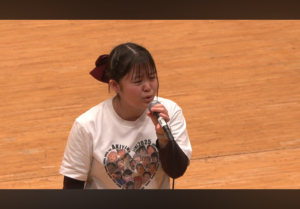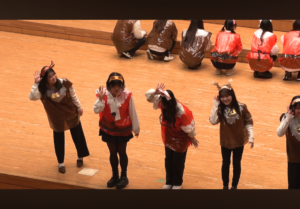毎日寒い日が続きますね。先日は学園にも雪が降り積もり、
ベンチには、誰かの作った小さな雪だるまが座っていました。
どんな季節の中にも、ちょっとした遊び心が小さな楽しみを生みますね。
雪と、学園の花の取り合わせも乙なもので、
寒さの中に宿る小さな息吹が感じられます。
普段とは違う、そのコントラストもまた良いものですね。
寒い中で目にする息吹も素敵ですが、
画面越しに眺めるきれいなお花もまた格別です。
温かいお部屋でゆっくりとくつろぎながら、ご覧ください。
ウメ
マツ
スイセン
バラ
キンセンカ
キンギョソウ
ローズマリー
毎日寒い日が続きますね。先日は学園にも雪が降り積もり、
ベンチには、誰かの作った小さな雪だるまが座っていました。
どんな季節の中にも、ちょっとした遊び心が小さな楽しみを生みますね。
雪と、学園の花の取り合わせも乙なもので、
寒さの中に宿る小さな息吹が感じられます。
普段とは違う、そのコントラストもまた良いものですね。
寒い中で目にする息吹も素敵ですが、
画面越しに眺めるきれいなお花もまた格別です。
温かいお部屋でゆっくりとくつろぎながら、ご覧ください。
ウメ
マツ
スイセン
バラ
キンセンカ
キンギョソウ
ローズマリー